
歴史的仮名遣いの問題は得点源!落とさないようにしっかり押さえておきましょう。
歴史的仮名遣いとは
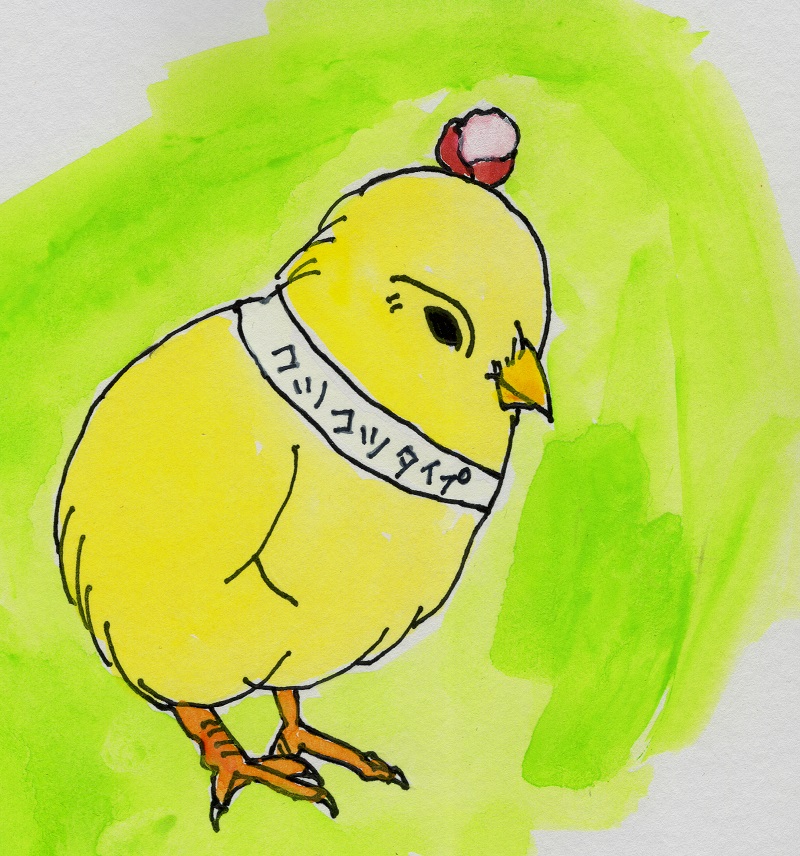
歴史的仮名遣いとはなんですか?

歴史的仮名遣いは平安中期頃の発音がもととなっている仮名遣いのこと。
現代仮名遣いは現代の発音で書かれたものです。
| 種類 | もとになっている発音 |
| 現代仮名遣い | 現代の発音 |
| 歴史的仮名遣い | 平安中期頃の発音 |
古文は歴史的仮名遣い(平安中期の発音)で書かれていますが、時代とともに発音が変化しているため、現代文の読み方と異なるケースが出てきます。
歴史的仮名遣いと現代仮名遣いの問題はここの違いをついてくるわけです。
歴史的仮名遣いのルール!現代仮名遣いに直すと?
古文の五十音図
まずは古文の五十音図から。
| ワ 行 | ラ 行 | ヤ 行 | マ 行 | ハ 行 | ナ 行 | タ 行 | サ 行 | カ 行 | ア 行 | |
| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | ア段 |
| ゐ | り | い | み | ひ | に | ち | し | き | い | イ段 |
| う | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | ウ段 |
| ゑ | れ | え | め | へ | ね | て | せ | け | え | エ段 |
| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | オ段 |
・ヤ行に「い・え」が、ワ行に「ゐ・う・ゑ」が入る
・ア行とヤ行の「い・え」、ア行とワ行の「う」は同じ発音
・現在はワ行の「ゐ・ゑ」は「い・え」と同じ発音だが、文語(古文に使用されている江戸時代までの書き言葉)では使い分けられている
(例)「ゐる(居る)」「いる(入る、射る)」など
※ア行とヤ行の「え」は以前は発音し分けられていたようですが、歴史的仮名遣いに反映されていません。この辺は専門的になってしまい、受験とはかけ離れていくので割愛
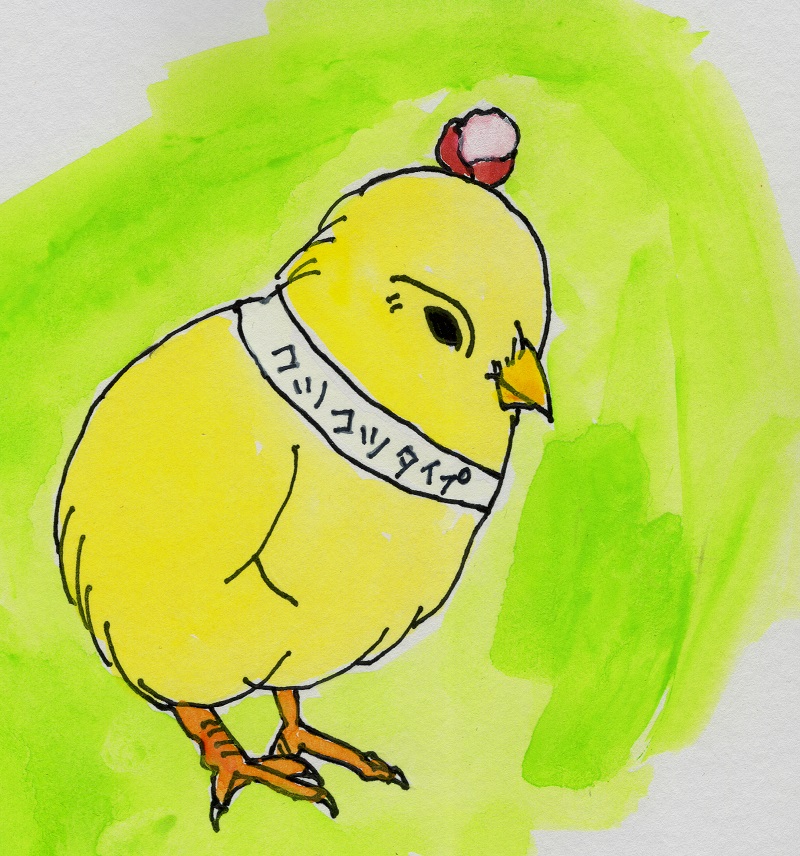
「ゐ」「ゑ」って初めて見るね。

「ゐ」「ゑ」は書けるようになってくださいね。
現代語の五十音とほとんど変わりませんが、数点加わっている部分があるのでそこをチェックしておきましょう。
同じ文字を二度使わずに47文字の清音を歌に詠み込んだのが「いろは歌」になります。
歴史的仮名遣いのルール一覧
| 歴史的仮名遣い | 現代仮名遣い(読み方) | 例 |
| は・ひ・ふ・へ・ほ ※語頭、助詞以外 | わ・い・う・え・お | 言ふ→言う |
| ぢ・づ | じ・ず | よろづ→よろず |
| ワ行の ゐ・ゑ・を ※「を」は助詞以外 | い・え・お | ゐる→いる ゑみ→えみ をり→おり |
| 語中の「む」 | ん | なむ→なん |
| くわ・ぐわ | か・が | くゎかく →かかく (過客) |
| ア段+う・ふ -au、-afu | オ段+う -ou(長音) | さうらふ →そうろう sau rafu →sou rou |
| イ段+う・ふ -iu、-ifu | イ段+ゅう -yuu(長音) | いみじう →いみじゅう imi jiu →imi jyuu |
| エ段+う・ふ -eu、-efu | イ段+ょう -you(長音) | けふ→きょう (今日) kefu→kyou |
高校入試では、このルールから歴史的仮名遣いの問題が出題されます。
をりふし(折節)→おりふし
※元々「をり」と「ふし」の2語から構成された言葉のためか、「を」は「お」と読むが、語中の「ふ」は「ふ」のまま。
のような、例外的な言葉もたまにありますが、こういったものは高校入試の歴史的仮名遣いの問題にはほとんど見られません。
また、濁点が入ると途端難しく感じるものもありますが、そこも基本にかえることが大切。
(例)
なでふ→なじょう
※でふ(defu)→ぢょう(dyou)→じょう(jyou)

基本のルールをきっちり押さえておくことが近道です。
過去60年分の古文を見てみたら…(公立〜難関校)
公立から難関校まで、過去60年分の古文の問題を見てみると、歴史的仮名遣いの出題は40問!
公立、中堅校、難関校に分けて出題傾向を見ていきましょう。
公立
・公立は9割が出題(各都道府県で大体1問、多い時で2問)
・公立でも独自問題を出す日比谷のような学校はない
語頭、助詞以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」を現代仮名遣いに直す問題が全体の6割を占めます。
次に多いのが「ア段+う・ふ」の問題。あとはルール一覧のどれかがパラパラ出ています。
公立は割とシンプルな問い方をしてきますが、1つの問題に複数の該当箇所がある場合は見落としに注意が必要です。
(例)
とほりあはせ→とおりあわせ
※語頭、助詞以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」が2カ所
中堅校
・中堅校は毎年1〜2問出題傾向にある
・難関校レベルに近い中堅校はあまり出ていない
中堅校でも語頭、助詞以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」を現代仮名遣いに直す問題が全体の6割を占めるという結果に。
3割程度が「ア段+う・ふ」、残りはルール一覧のどれかが出題されています。
シンプルな問題が多いですが、公立同様、1つの問題で複数の該当箇所があったり、いくつかのルールを組み合わせているケースも見られます。
(例)
いひをしへて→いいおしえて
※語頭、助詞以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」とワ行の「ゐ・ゑ・を」
難関校 ※駿台偏差値60超
・難関校レベルになるとほとんどない(あってもたまに、5〜6年前とか)
ご察しの通り、難関校ほど歴史的仮名遣いの設問は出題されない傾向にあります。灘、開成をみても直近5〜6年で皆無。
基礎知識がある事前提で、現代語訳や内容把握の設問が出題されています。しかも記述多め。
考える問題が多く、読む量も圧倒的に増えてくるのが特徴です。
まとめ
・古文は歴史的仮名遣い(平安中期の発音)で書かれているため、現代の発音とは異なる
・現代仮名遣いは現代の発音で作られている
・歴史的仮名遣いのルールを押さえる
・公立〜中堅校でよく出題される
古文単語をどこまで覚えるべきか?整理しました
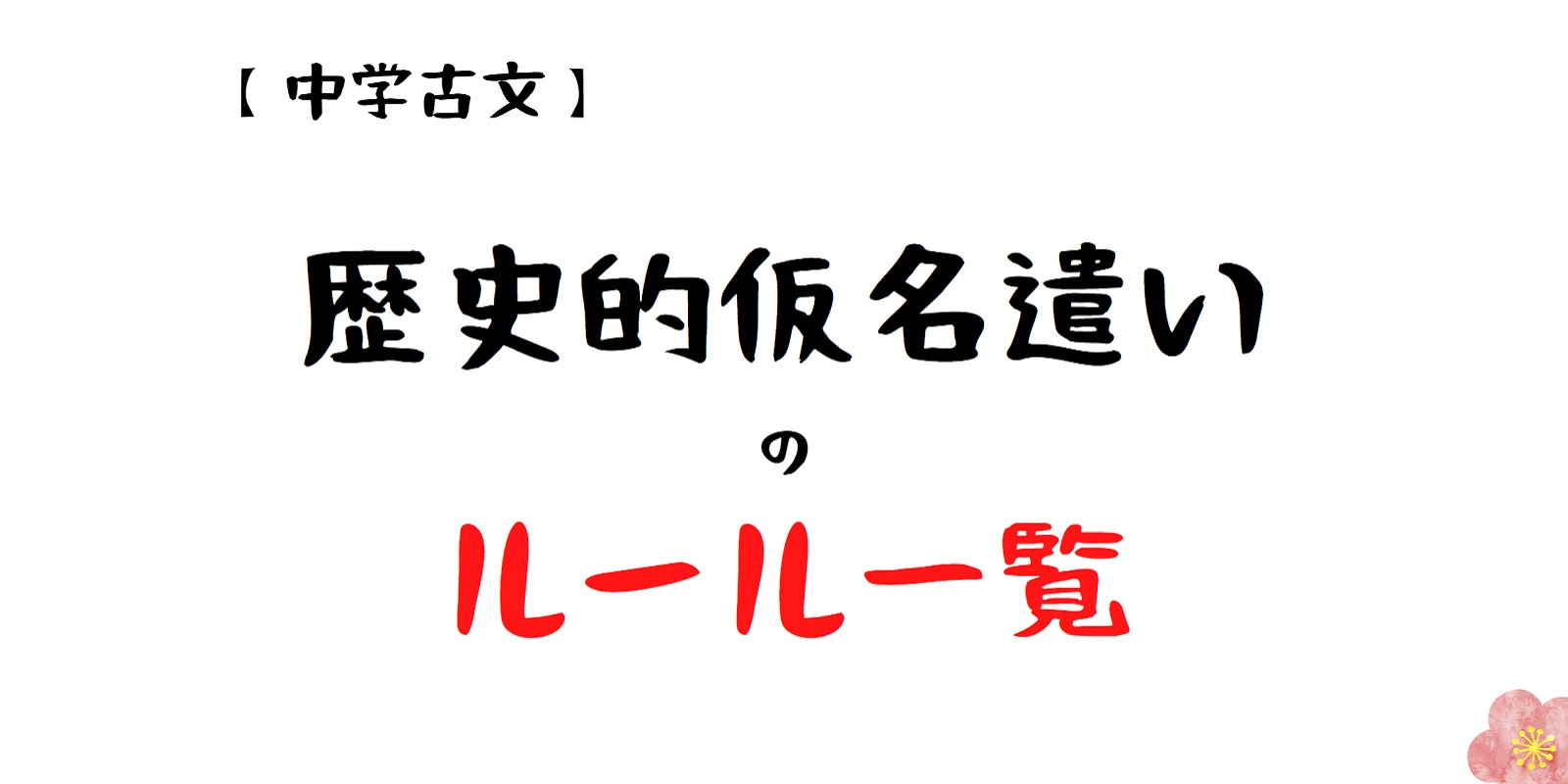
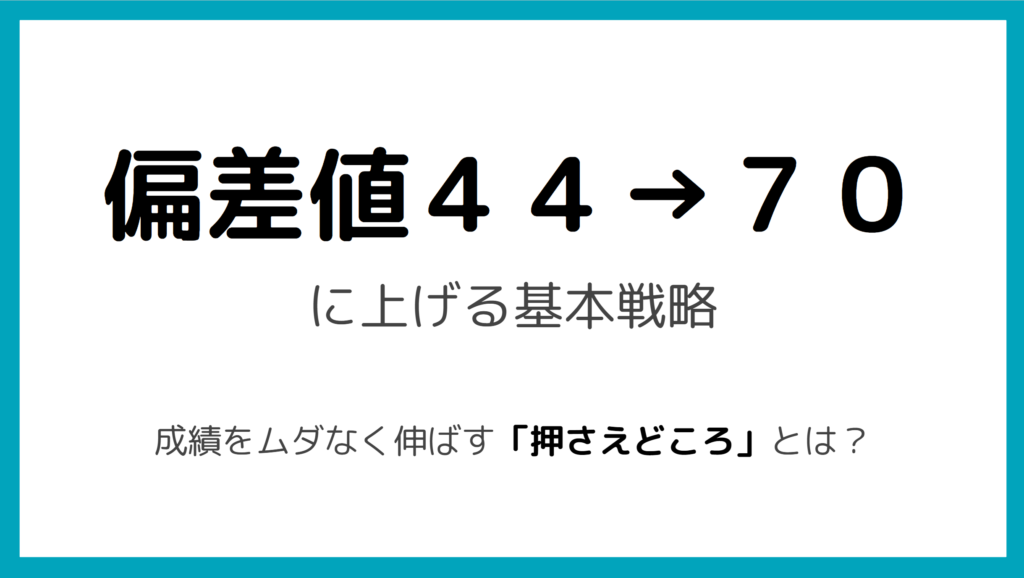

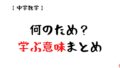
コメント